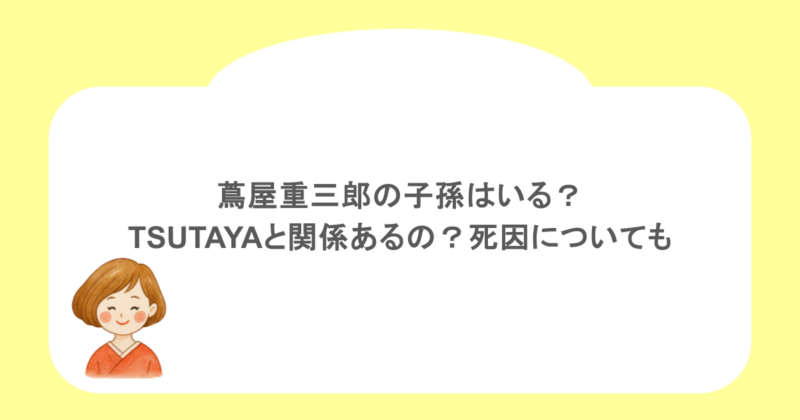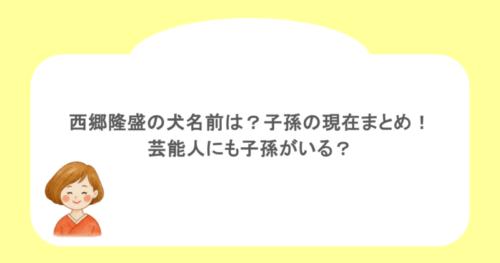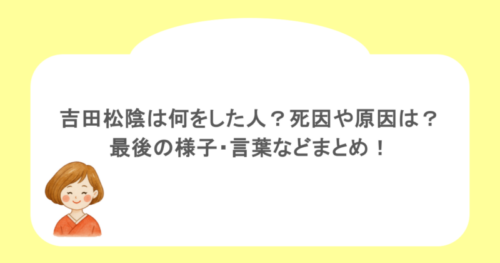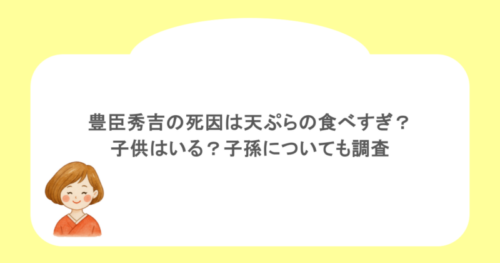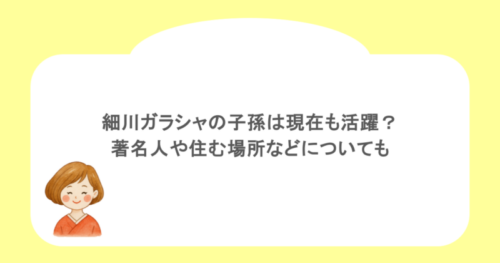歌川広重や葛飾北斎、東洲斎写楽などを世に送りだした蔦屋重三郎をご存知でしょうか?横浜流星 大河ドラマ主演をしている『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のモデルだったこともあり、注目している人もいるようですね。
そこで今回は蔦屋重三郎の子孫は存在するのか、TSUTAYAとの関係・死因についても調査しましたので皆さんにご紹介していきます。
蔦屋重三郎の子孫はいるの?跡継ぎや事業についても
江戸時代の天才出版プロデューサーとして知られる、蔦屋重三郎の子孫について探ってみましょう。
妻がいたって本当?
蔦屋重三郎に妻がいたことは記録から確認できますが、人物像や名前などについては不明です。そのため、後世の研究や創作の中で重三郎の妻は、さまざまに描かれました。
映画『HOKUSAI』では、町娘「トヨ」が妻として登場したり、2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、橋本愛さんが妻役「てい」を演じたりしています。両者ともフィクションに基づいて設定されており、実在の裏付けがあるわけではありません。
子どもや子孫はいる?
血縁の子どもや子孫が、蔦屋重三郎にいたかどうかは史料から確認できません。重三郎が亡くなった後に、蔦屋の屋号は番頭が婿養子として家を継いだと伝えられているため、直系の後継ぎがいなかった可能性があります。
しかし、当時の記録は限られているので子どもの有無を完全には否定できませんが、重三郎直系の子孫が続いている証拠はないようです。
跡継ぎは誰?
蔦屋の家業を重三郎が亡くなった後に継いだのは、番頭を務めていた勇助と言われています。勇助は婿養子として蔦屋家に入り、二代目「重三郎」を名乗りました。出版事業を引き継いだ勇助は、葛飾北斎が挿絵を描いた狂歌本『潮来絶句集』を手がけましたが、その装丁が華美であったことから、処罰を受けたようです。
二代目の没後は、息子の祐助が三代目を襲名し、四代目には後の戯作者としても知られる「二世三亭春馬」が継承しました。五代目は喜多川竹吉が、名を継いだとされています。
蔦屋重三郎の死後の事業は?
重三郎の死後、出版事業は屋号『耕書堂』として受け継がれ、江戸時代から明治初期にかけて、蔦屋の名は出版業界で一定の影響力を保ち続けました。
当主たちは、重三郎が築いた事業の基盤を大切に守りながら、時代の変化に対応して新たな出版ジャンルに挑戦。浮世絵や教育書など、当時の人々の関心や需要に応じた書籍の刊行を進めることで、事業の幅を広げたようです。
蔦屋重三郎とTSUTAYAの関係は?
『TSUTAYA』を経営しているのは蔦屋重三郎の子孫ではなく、両者は一切関係ありません。
創業者の増田宗昭さんが『TSUTAYA』と名付けたのは、祖父が営んでいた置屋の屋号が『蔦屋』だったからとされています。
また、屋号が置屋に由来していることよりも、「蔦屋重三郎にあやかりたい」とする方が好印象のため、後付けしたと言われているようです。そのため蔦屋重三郎の子孫は『TSUTAYA』の創業者ではないことは確かです。
蔦屋重三郎の死因は?最後や死後についても
謎が多いと言われる蔦屋重三郎の死因や最後、死後について1つずつ見ていきましょう。
死因と享年は?
蔦屋重三郎は西暦1797年5月31日(寛政9年5月6日)に脚気で亡くなり、享年48歳でした。脚気とはビタミン不足によって起こる疾患で、心不全や末梢神経障害などの症状が現れます。
江戸時代の日本では白米中心の食生活が一般的だったので栄養が偏りやすく、脚気を発症する人が多かったようです。
また、過度の飲酒も発症リスクを高める要因とされているため、重三郎も食生活や生活習慣の影響を受けて、病に倒れたと考えられます。
蔦屋重三郎の生涯年表
波乱に富んだ蔦屋重三郎の生涯は、1750年に江戸吉原で誕生したところからスタート。1773年には、吉原大門の前に書店を開きます。1774年に吉原細見の販売・出版を手がけ、1777年には書店として独立しました。
1783年・日本橋通油町に進出し、朋誠堂喜三二や山東京伝、恋川春町たちと親交を深めて戯作や狂歌本の刊行に注力します。しかし、1791年には山東京伝の洒落本・黄表紙が摘発されて身上半減の処分を受けました。1794年には東洲斎写楽の役者絵を出版し、48歳の若さで1797年に生涯を閉じています。
蔦屋重三郎の最後の言葉とは?
亡くなる最後に、「私は今日の昼時には死ぬよ」と言い残したとされる蔦屋重三郎。しかし、その日の夕方になっても亡くならず、「もう幕が下りて、拍子木が鳴ってもいいのにずいぶん遅いな」「拍子木はまだ鳴らねぇのか?」などと、自分の最期について面白おかしく表現したようです。
重三郎は最後の言葉を残した直後、静かに息を引き取り、享年48歳で生涯を閉じました。江戸の娯楽の達人である重三郎は、死の間際にも笑いを忘れなかったようです。
蔦屋重三郎の死後に起きた出来事は?
重三郎の死後、日本は西欧列強の接近により時代の変化に直面しました。蔦屋重三郎が亡くなった頃には、1792年にロシアの特使が蝦夷地・根室に入港して通商を求める事件が起こっています。1800年には、伊能忠敬が蝦夷地の測量を開始しました。
その後も時代は急速に動いて、1853年にはペリーが浦賀に来航し、1868年の明治維新で江戸幕府が滅亡。日本は一気に近代化を進め、蔦屋重三郎が見出した才能や文化は、後に海外の多くの偉人や文化に影響を与えています。
まとめ
今回の記事では、江戸の出版界を代表する豪商である蔦屋重三郎の子孫の存在を中心に、TSUTAYAとの関係や死因について紹介しました。
重三郎に子どもがいた可能性もあるようですが、直系の子孫が続いている証拠は見当たらないようですね。2025年放送の大河ドラマ『べらぼう』を鑑賞し、蔦屋重三郎の人生に触れてみましょう!